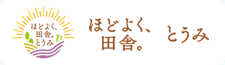高額療養費・限度額適用認定証・標準負担額減額認定証・特定疾病療養受療証
高額療養費制度
1カ月間の医療費の一部負担金が高額になったとき、自己負担限度額を超えた部分が、高額療養費としてあとから支給されます。対象となる方には、市から通知を送付しております。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
所得 ※1 | |||
ア | 901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | |
オ | 住民税非課税世帯 ※2 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)
| 窓口 負担 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
| 3割 | 現役並みⅢ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降は140,100円 ※4〉 | |
| 現役並みⅡ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降は93,000円 ※4〉 | ||
| 現役並みⅠ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降は44,400円 ※4〉 | ||
| 2割 | 一般 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間限度額144,000円 ※1) | 57,600円 〈4回目以降は44,400円 ※4〉 |
| 低所得者Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ※3 | 8,000円 | 15,000円 | |
※1 年間限度額は8月から翌7月までの累計額に対して適用されます。
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4 過去12ヵ月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から限度額が下がります。
※5 限度額は医療機関・薬局ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに計算をします。また、同一の薬局の場合は同一の医療機関から処方された分ごとに計算します。
※6 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代は医療費の対象になりません。
非自発的失業者に対する自己負担限度額の判定について
非自発的失業のため保険税の軽減を受けた世帯について、高額療養費の所得区分が変更される場合があります。
【所得区分計算】
非自発的失業者の所得のうち給与所得を30/100とみなして所得判定を行います。
計算した結果、均等割2割軽減に該当する場合は、医療費の限度額の所得区分が住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ)と同じになります。
【適用期間】
離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から保険税軽減終了後の7月末まで適用されます。ただし、離職日の翌日が1日の場合はその月から適用されます。また、世帯全体が職場の健康保険から新たに国民健康保険に加入された場合は、保険税軽減が開始される月から適用されます。
◆70歳以上の方で一定の所得(課税所得が145万円)以上の方◆
同一世帯にいる70歳以上の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、区分が「一般」になります。
「一般」となる世帯
70 歳以上の方の人数 | 70 歳以上の方の合計収入 |
|---|---|
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
限度額適用認定証について
医療機関等の窓口での1か月の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなる制度があります。
※同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となる場合があります。
限度額適用認定証の提示・申請が不要になりました
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムで適用区分の確認ができれば、限度額認定証の提示が不要になりました。(システムを導入しているかは、受診する医療機関等にお問い合わせください。)
※以下の場合は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。事前に市役所で申請手続きをしてください。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受診をする場合
・国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
限度額適用認定証を申請する場合
マイナ保険証をお持ちの方は、令和7年8月1日以降は申請の必要はありません。マイナ保険証をお使いください。
◆対象者◆
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で区分が「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方
・マイナ保険証をお持ちでない方
◆手続きに必要なもの◆
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
標準負担額減額認定証と減額差額申請について
住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証の申請により標準負担額1食あたり510円が下記の金額に減額されます。
| 区分 | 1食あたり標準負担額 | |
|---|---|---|
| 一般(減額なしの場合) | 510円 | |
| 住民税非課税世帯の方※1 | 90日までの入院 | 240円 |
| 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院※3 | 190円 | |
| 高齢受給者証をお持ちの方で低所得Ⅰに該当する方※2 | 110円 | |
※1:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯の方
※2:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯の方であって、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
標準負担額減額認定証の提示・申請が不要になりました
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムで適用区分の確認ができれば、標準負担額減額認定証の提示が不要になりました。(システムを導入しているかは、受診する医療機関等にお問い合わせください。)
※以下の場合は医療機関等へ標準負担額減額認定証を提示する必要があります。事前に市役所で申請手続きをしてください。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受診をする場合
・国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
・所得区分「オ」または「低所得者Ⅱ」の期間で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合(入院時の食事代が減額になります)
標準負担額減額認定証を申請する場合
マイナ保険証をお持ちの方も以下の場合は、申請が必要です。事前に市役所で申請手続きをしてください。
◆対象者◆
・住民税非課税世帯の方で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える方
◆手続きに必要なもの◆
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・入院期間が91日以上であることがわかる書類(領収証など)
標準負担額認定証の提示ができず入院時の食事代の減額が受けられなかった場合
本来の負担額との差額を申請によりお支払いします。
◆食事差額の申請に必要なもの◆
・領収書
・預金通帳など振込口座がわかるもの
・印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合)
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
特定疾病に関する給付
高額の医療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示することで、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人口透析を要する70歳未満の上位所得者(区分ア、イ)の方は、自己負担限度額が2万円となります。
◆厚生労働大臣が指定する特定疾病◆
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
◆手続きに必要なもの◆
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111 (内線1231、1232、1234、1235)
電話:0268-75-8810 (直通)
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年11月5日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)