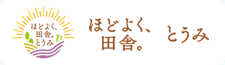国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、私たちがいつ、どんなときにかかるかわからない病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入や資産に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという社会保障制度を支えるものです。
国民健康保険の加入者
東御市内に住んでいる方(3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方を含む)で、他の医療保険に加入している方とその扶養家族及び生活保護を受けている方以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
納税義務者
国民健康保険税では世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国保加入者でない場合でも、納税義務者となります。(擬制世帯主)
国民健康保険税と後期高齢者医療制度の関係
平成20年度に「後期高齢者医療制度」を支えるための支援金制度が創設されて以降は、国民健康保険税においても基礎課税(医療)分、介護納付金分(40歳から65歳未満)に加え後期高齢者支援金等分を合算して課税しています。
国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、基礎課税(医療)分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分を合算して決められます。また、算定の基礎となるのは前年中の総所得金額です。
※総所得金額・・・社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの各種所得控除前の金額
40歳未満の方 | 医療分+後期高齢者支援金等分 |
|---|---|
40~64歳の方 | 医療分+後期高齢者支援金等分+介護納付金分 |
65歳以上の方 | 医療分+後期高齢者支援金等分(ただし、別途、介護保険料が徴収されます) |
令和7年度国民健康保険税率
区 分 (納める方の年齢) | 基礎課税(医療)分 (0歳から74歳まで) | 後期高齢者支援金等分 (0歳から74歳まで) | 介護納付金分 (40歳から64歳まで) |
①所得割額(国保加入者の所得に対する課税割合) | 6.7% | 2.5% | 2.3% |
②資産割額(国保加入者に係る固定資産税額に対する課税割合) | 5.6% | 1.9% | 0.9% |
③均等割額(1人当たり) | 20,100円 | 8,300円 | 9,000円 |
④平等割額(1世帯当たり) | 20,600円 | 7,400円 | 8,200円 |
賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
年間保険税額は①+②+③+④ (ただし、賦課限度額までとなります。) | |||
算出上の注意事項
1 介護納付金の計算
・ 年度途中で40歳になる方は、40歳に到達した翌月に再計算した国保税の更正通知を送付します。
・ 年度途中に65歳になる方は、65歳になる前月までの介護納付金を年度末までの納期に分けて納めます。
2 月割課税
・年度途中の加入・脱退のときは、加入の月から脱退の前月までの月割で計算します。
3 軽減
・一定以下の所得世帯には均等割額と平等割額の税負担を配慮して、軽減が適用されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主及び被保険者※の前年の所得の合計額で比較) |
7割 | 43万円 +10万円×(給与取得者等の数-1)以下 |
5割 | (43万円+30.5万円×被保険者数※) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | (43万円+56万円×被保険者数※) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※ 国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行した場合も含みます。
国民健康保険税の減免について
不慮の事故や災害などの理由で、どうしても国民健康保険税を納めることができないときは、納税を延期したり(徴収猶予・分割納付等については、税務課にてご相談ください。)、減免される制度がありますので、まずはご相談ください。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
解雇や雇い止めなどの理由により離職された方(非自発的失業者)の国民健康保険税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。
対象者は次の要件に該当する方
1. 離職日時点で65歳未満である方。
2. 離職日の翌日から翌年度末までの間に、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方(特定受給資格者・特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です)。
軽減内容
非自発的失業者本人の前年給与所得を30/100として税額算定します。
給与所得がない、または給与所得の申告がない場合は、軽減になりません。転入された方は所得の判明時期により判定が遅れる場合があります。
また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者本人の前年給与所得を30/100として税額算定します。
なお、計算した結果、均等割2割軽減に該当する場合は、医療費の限度額の所得区分が住民税非課税世帯と同じになります。(低所得者Ⅱ)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。(例:令和7年8月1日に離職された場合は、令和9年3月まで)
申請に必要なもの
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(公共職業安定所で交付されます)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
産前産後期間の国民健康保険税の免除について
産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が令和6年1月から実施されています。
対象者は次の要件に該当する方
1.令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。
2.妊娠85日(4ヶ月)以上の出産の方(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
軽減内容と軽減期間
対象年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(産前産後期間といいます。)相当分が減額されます。
●単胎の方
●多胎の方
※産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
申請に必要なもの
・出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳など)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
世帯員の後期高齢者医療制度加入に伴う国民健康保険税の軽減について
・同一世帯中の国保に加入している方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保被保険者が世帯にお一人になる場合、最初の5年間は平等割の2分の1が軽減され、さらにその後の3年間は4分の1が軽減されます。(申請の必要はありません)
・同一世帯員が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳)が、新たに国保に加入し保険税を納めることになった場合、所得割、資産割は免除されます。また、最初の2年間は7割・5割軽減に該当する場合を除き、均等割の2分の1が軽減になり、さらに、被保険者が1人の場合には平等割も2分の1が軽減されます。(申請が必要になります)
未就学児の国保税均等割額の軽減について
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国保被保険者(以下「未就学児」)の均等割額について、医療分と後期高齢者医療支援金等分の2分の1が軽減されます。軽減対象世帯となっている未就学児については、軽減後の均等割からさらに2分の1が軽減されます。(申請の必要はありません)
国民健康保険税の納付方法
国保に継続加入している方、あるいは5月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は、6月中旬に納税通知書を納税義務者あてにお送りします。通常納期は6月末(1期)に始まり、翌年3月末(10期)までの年間10回で納めていただくことになります。
年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは「月割り」で計算し、届け出をした翌月の中旬に納税通知書又は更正決定通知書をお送りします。
国民健康保険税の納付には、口座振替を利用すると便利です。納め忘れがなく便利で確実な口座振替をご利用ください。
国民健康保険税の納付書には、eLTAX(地方税共通納税システム)を導入しています。eLTAXを利用することで、eL-QR(地方税統一QRコード)対応の金融機関での納付やスマートフォン決済アプリでのお支払い、また地方税お支払いサイトからeL-QRを読み取ることで、クレジットカード、インターネットバンキングなどの電子納付を行うことができます。
*QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
年金からの天引き(特別徴収)
次の全てに該当する世帯主の国保税は、その方の年金から天引き(特別徴収)されます。
特別徴収の対象とならない方は、従来どおりの方法(普通徴収)で納めることとなります。
(1) 世帯主が市の国民健康保険の加入者で、その世帯主及び世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満
(2) 世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している。
(3) 国保税額と世帯主自身の介護保険料額との合算額が年金受給の2分の1を超えない。
特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。(自動的に変更させていただきます。)
なお、お支払方法はお申し出いただくことにより、特別徴収から口座振替に変更することができます。一度お申し出いただくと、翌年度以降も特別徴収への変更希望がない限りは、口座振替を継続させていただきます。
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
特別徴収 (年金天引き) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
普通徴収 (口座振替・ 現金納付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国民健康保険税の社会保険料控除について
所得税、市県民税の申告における国民健康保険税や国民年金保険料などの社会保険料控除については、ご本人や生計を一にする配偶者その他の親族の負担する社会保険料を支払った場合には、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。
年金から特別徴収されている場合、その国保税を支払った方は年金受給者本人となります。(年金受給者本人以外の方の社会保険料控除とすることはできません。)
特別徴収に代えて、口座からのお支払いに変更した場合は、その国保税を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
市民課国保年金係
電話:0268-75-8810 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年10月16日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)